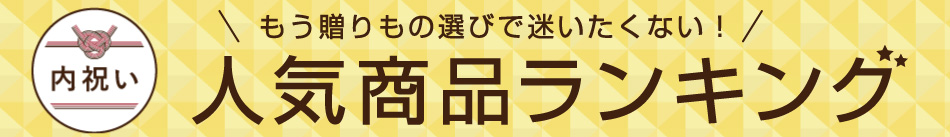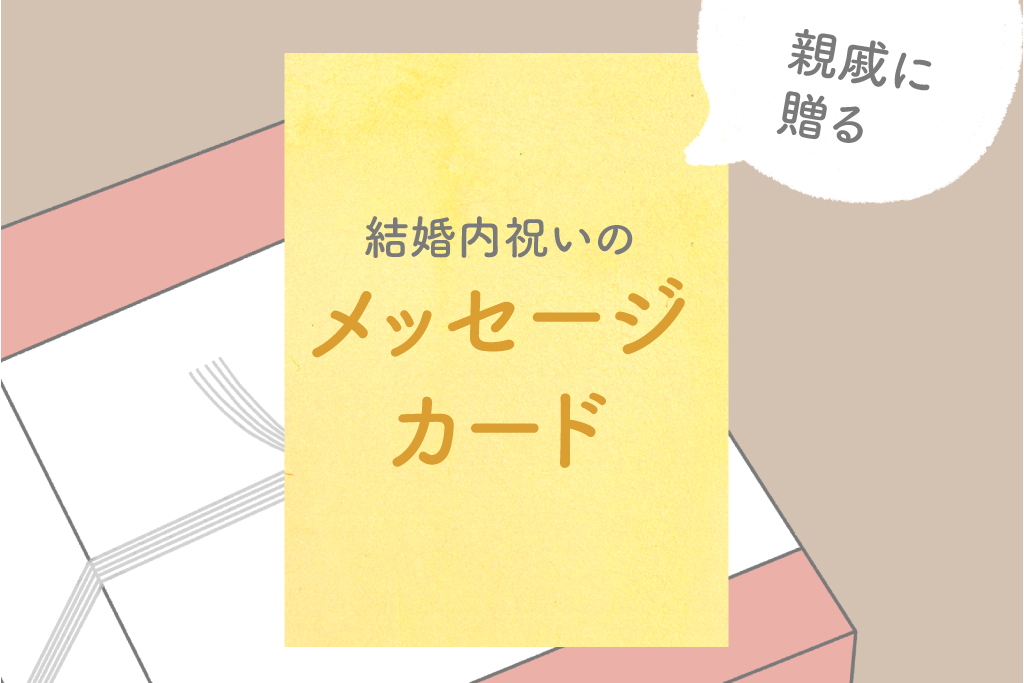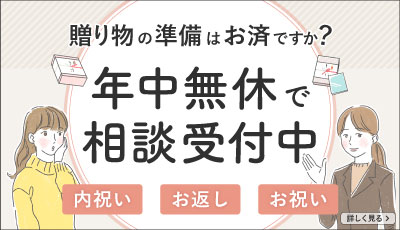花笑むという言葉を聞いたことがありますか?
花が笑うという字を見て、何となく意味が分かる人もいるかも知れません。
でも、現代では、なかなか日常生活で花笑むという言葉を見聞きしないため、全く知らないという人もいるでしょう。
ここでは、そんな「花笑む」という言葉の意味から使い方まで、詳しくご紹介します。
花笑むとは?いつから使われているの?
花笑む(はな・え(ゑ)・む)という言葉の歴史は意外と古く、7、8世紀頃には既に使われていたものであるといわれています。
日本最古の和歌集と名高い万葉集では、既にこの言葉が使われていて、幾つかの歌の中に「花笑む(花笑み)」という表現が出てきます。
「花笑む」という言葉や表現は、昔から親しまれてきた、いわゆる大和言葉というものですが、現代ではなかなか聞く機会や、目にする機会がありません。
では、花笑むというのは、一体どんな意味を持つ言葉なのでしょうか?
花笑むの意味は?どんな状態をいうの?
花笑むには、「花が咲く、実をつける、固いツボミが開く、満面の笑み」という意味があります。
花(特に百合)が咲くことを意味するのですが、花笑むの笑も、本来は咲という字を使用していました。
咲く=わらう(笑む)という意味があるからです。
慣用句に「鳥鳴花咲」というものがありますが、これも昔は「鳥が鳴き花がわらう」と読まれていました。
でも、現代では解釈がしやすいように「鳥が鳴き花が咲く」となったと言われています。
同じ【わらう】でも、笑うと咲うでは表現の仕方が少し異なります
笑うは口元がほころぶというもので、咲うはつぼみがほころぶというものになるのです。
笑むという言葉にも、つぼみがほころぶ、果実が実り弾けるというような意味があります。
また、花笑むには「花が咲くような華やかな笑顔」や「咲いた花のように微笑む人」という意味もあり、擬人法のように人を表現する際にも使用されます。
そのため、「花笑む人」という使い方をした場合、「百合の花が咲くように微笑んでいる人」というような状態を意味します。
花笑むの使い方は?どんな時に使うの?
花笑むという言葉が素敵な状態を表わす、華やかで美しい意味があるということが分かりました。
でも、日常生活でどのように使えば良いのでしょうか?
一般的な会話では、なかなか使うことがありませんし、使い方に悩んでしまうかも知れませんが、俳句や短歌、和歌の世界では、夏の季語として親しまれています。
花が咲き誇る夏の情景や、微笑んでいる情景を表わすのに使われているのです。
また、挨拶文に使っても美しいものです。
例えば、結婚電報などで、「ご結婚おめでとうございます。ウェディングドレスを着て花笑む○○さんが、目に浮かびます。お二人なら、幸せの花をたくさん咲かせられることでしょう。末永くお幸せに」
というように使用すれば、とても華やかで美しいお祝いの言葉となります。
「花笑む人」と表現すると、歓びに満ち溢れたイメージになりますので、成人のお祝いや入学のお祝いなど、嬉しい出来事のお祝いの際に贈る言葉としても人気があります。
時候の挨拶でも、「花笑む季節となりました」と使うと、とてもオシャレですね。
使い方次第で、とても綺麗な情景が想像できる文章となりますので、是非使ってみましょう。
なぜ花笑むは百合なの?
花笑む・花笑みという言葉には、百合の花が咲く様という意味があります。
では、なぜ百合だったのでしょうか?
百合にはカサブランカなど西洋のものから、日本の姫ゆり、笹ゆり、山ゆりなど様々な種類があります。
日本では、古来から草深い野に咲くものもあり、どこからともなく良い香りが漂い、その香りに導かれて近付くと美しい百合が咲いているということもあります。
そのため、昔から百合は傍らにそっと佇む美女に例えられてきました。
美しい女性の優雅な立ち振る舞いを表わしているのです。
特に笹ゆりは、細い茎の割りに大ぶりの花を咲かせるのが特徴です。
そのため、笹ゆりが風に揺れる姿は、微笑む美女を思わせるのです。
万葉集では、百合の花を詠んだ歌が十一首もあり、中でも笹ゆりは髪飾りにされるほど、万葉の人々にも親しみ深いものでした。
現代では自生する笹ゆりが少なくなっていますので、身近と言われてもピンとは来ないかも知れませんが、昔はよく目にされていたのでしょう。
万葉集で詠まれた「花笑む」は?
前述の通り、万葉集では「花笑む」を使った歌が幾つか詠まれています。
万葉集の1257では、
~道の辺の 草深百合の花笑みに 笑みしがからに 妻と言ふべしや~ 大伴家持
というものがあります。
この句は、男性からの目線と女性からの目線で歌の解釈が変わる珍しいものです。
男性からの目線で解釈すると・・・草が生い茂る道端で咲く百合のように、貴方は優しく私に微笑みかけてくれました。もうそれだけで、私の妻といっても良いでしょうか。と女性への求愛・プロポーズの句になります。
一方、女性からの目線で解釈すると・・・草生い茂る道端に微笑むように咲いている百合のように、ただ微笑みかけただけであなたの妻になれるのもでしょうか。という男性からの求愛、プロポーズをお断りする句です。
また、万葉集の4116では、
~夏の野の さ百合の花の花笑みに にふぶに笑みて逢はしたる~ 大伴家持 (一部抜粋)
というものがあります。
これは、夏の野に咲く百合(または小百合)の花のように微笑んで、私と逢ってくれました。
という逢瀬を喜ぶ男性を思わせるものになっています。
どちらも、野に咲く百合のように微笑む、美しい女性を「花笑む」で例えています。
店名などに意外と多く使用されている
花笑む、花笑みという言葉は、お店や施設の名前などに多用されています。
様々なジャンルのお店に使用されています。
唄や物語のタイトルに使われたりすることもあります。
明るいイメージのある縁起の良い言葉なので、使いやすいのでしょう。
また、花笑と書いて「はなえ」と読ませる名前などに使われる事もあります。
香川県にある「国営讃岐まんのう公園」では、花笑フォト(はなえみふぉと)というイベントを行っていて、綺麗、楽しい、嬉しいという写真を募集し、ホームページ上のフォトギャラリーで紹介しています。
このように、聞き慣れない言葉だなと感じていても、意外と身近に存在していたりもするのです。
大和言葉は美しい!
花笑むという言葉は、いわゆる大和言葉と呼ばれるものです。
大和言葉というものは、飛鳥時代の頃まで大和飛鳥や大和国で話されていたとされる言語です。
漢語や外来語を除く日本語の固有語を指します。
つまり、日本に大陸文化が伝来するよりも前から日本国内で使われていた言葉なのです。
時代が進むと、和歌などに使用されるようになり、幕府や宮中などの上流階級が主に使う言葉となりました。
花笑む、花笑みに似た言葉に「山笑う(やまわらう)」というものがあります。
これは、花笑むと同じく大和言葉というものになります。
冬の間眠って居た山々が、春になり緑や活気を取り戻し、笑っているような明るいイメージを持つ言葉です。
春の季語としても使われています。
大和言葉には、他にも様々なものがあります。
蛙の目借時(めかりどき)、猫の恋、花曇りなどは春を表わす言葉です。
梅雨の月、旱星(ひでりぼし)、雲の峰などは夏を表わす言葉です。
秋は、虫あわせ、野山の錦、水澄むなど、冬は、返り花、山眠る、冬ざれなどで表されます。
また、花笑むが百合の花を表現しているように、他の草花を表わしている大和言葉もあります。
例えば、「いずれは菖蒲(あやめ)か杜若(かきつばた)」という言葉は、菖蒲や杜若、花菖蒲(はなしょうぶ)などは、どれも良く似ていて混乱します。
この混乱状態を表わした言葉です。
「花のかんばせ」という言葉は、花のように美しい顔のことをいいます。
よく知れば知るほど魅力的な大和言葉を使ってみるのも良いかも知れません。
まとめ
花が咲く様に笑うという意味を持つ「花笑む」という言葉は、日本古来から使われている美しい大和言葉のひとつです。
大和言葉は、現代でも変わらず一般的に使われているものから、なかなか見聞きする機会の無いものまであります。
花笑むは、百合の花が咲く姿を表現しているのですが、万葉集などでは「百合の様に微笑む美しい女性」を指しています。
お店などの名前に使われることもありますが、お祝いの際に掛ける言葉などに使用すると、華やかで美しいオシャレなものになります。
是非、日常生活にも気軽に取り入れてみましょう。
関連記事
親戚に贈る結婚内祝いのメッセージの書き方と相手別の例文を紹介
今後の生活の助けになればと高額な結婚祝いを贈ってくれる親戚や、遠方で結婚式 … 記事を読む
関連記事
友人から出産祝いをもらったので、何かお返ししたいと思っていませんか?と … 記事を読む