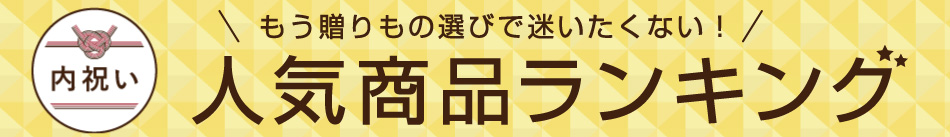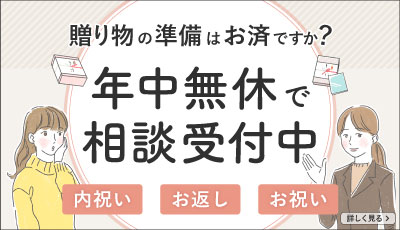処暑とは、一年を24等分(15日ずつ)にして季節を表す名称をつけた「二十四節気(にじゅうしせっき)」のひとつです。
秋の節気のうち2番目(立秋の次)にあたりますが、昼の気温はまだまだ高く夏バテに気をつけたい時期。
今回は、そんな処暑の意味や過ごし方、旬の食べ物、季節の草花、行事などを解説します。
手紙に使える「処暑の候」の例文もご紹介していますので、ぜひ参考にしてくださいね。
処暑は8月23日頃!暑さが和らぎ始める時期のこと

処暑の読み方は「しょしょ」。
8月23日頃を指す二十四節気で、「暑さが落ち着く時期」を意味しています。
「処」という漢字には「落ち着く」という意味があります。
処暑は読んで字のごとく、暑さのピークが終わり、だんだん秋に向かい始めるシーズンなんですね。
暦の上では初秋だけどまだまだ残暑に注意!
処暑のひとつ前の二十四節気は「立秋」、ひとつ後ろが「白露(はくろ)」です。
立秋は「秋が始まる時期」、白露は「大気が冷えて草花に朝露がつき始める頃」という意味。
立秋の次にきていることからもわかるとおり、処暑は暦の上では秋にあたります。
地域にもよりますが、朝夕は徐々にひんやりしてきたり、虫の音に秋の気配を感じられたりするでしょう。
山野では赤とんぼも見られます。
とはいえ、8月下旬の平均気温は東京で26.1℃。
まだまだ残暑が厳しいシーズンですから油断はできませんね。
夏バテになりやすい時期でもあるため、室内ではクーラーをつける、しっかり水分補給をするなど体調管理に気を配りましょう。
2023年の処暑は8月23日・期間は8月23日~9月7日
各二十四節気は、特定の日付を表す場合と、次の節気までの期間を意味する場合があります。
2023年の処暑はそれぞれ以下のとおり。
- 日付は8月23日
- 期間は8月23日~9月7日
各節気の期間はおよそ15日ですが、毎年必ず同じ日付から始まるわけではありません。
処暑も8月22~24日のなかで日付が変動するので、時候のあいさつなどに「処暑」を使う場合は気をつけてくださいね。
2023年の処暑の日付は8月23日です。
処暑の期間は、次の節気である「白露」の前日まで。
2023年の白露は9月8日なので、処暑の時期は8月23日~9月7日です。
ちなみに残暑見舞いを送る一般的な時期は、立秋(8月7日頃)~8月31日までだとされています。
遅くとも9月上旬までに出さなければなりません。
処暑は残暑見舞いを送っても失礼にならないギリギリのタイミング。
この期間が終わるまでに残暑見舞いを出すといいでしょう。
処暑は台風が多い!?暴風雨の起きる「雑節」がある
日本には二十四節気のほかに、季節の移り変わりを表す「雑節(ざっせつ)」という暦日があります。
- 二百十日(にひゃくとおか)…立春の209日後。2023年は9月1日
- 二百二十日(にひゃくはつか)…立春の219日後。2023年は9月11日
これらの雑節は「台風が多い、暴風雨が起きる日」だとされています。
稲が開花するシーズンのため、昔の人たちが「油断せずに台風に備えよう」と考えたのが由来だそうです。
二百十日は毎年9月1日頃なのでちょうど処暑の期間にあたりますが、実際の統計ではこの頃に特別台風が多いわけではありません。
とはいえ、8月~9月は一年のなかでも台風の接近・上陸が多いシーズン。
処暑になったら昔の人に倣ってしっかりと台風対策をしておくと安心ですね。
また8月末は比較的に降水量も多いので、折りたたみ傘を持ち歩くのがおすすめです。
処暑の七十二候は「綿柎開」「天地始粛」「禾乃登」

各二十四節気には、それぞれの期間を3つに分けて一年を72等分(約5日ごと)にした「七十二候(しちじゅうにこう)」という期間があります。
処暑の七十二候は以下の3つ。
| 読み方 | 期間 | 意味 | |
| 綿柎開 | わたのはなしべひらく | 8月23日~8月27日頃 | 綿を包む花の萼(がく)が開く |
| 天地始粛 | てんちはじめてさむし | 8月28日~9月1日頃 | 暑さがおさまり始める |
| 禾乃登 | こくものすなわちみのる | 9月2日~9月6日頃 | 稲を始めとする穀物が実る |
処暑のなかでも細かく季節の移ろいを表した指標なので、気候や草花の様子と照らし合わせてみると楽しいですね。
ていねいな手紙に使いたい「処暑の候」の例文
お礼状やビジネス目的のお手紙には、二十四節季や七十二候を使った「時候のあいさつ」を盛り込むとていねいで好印象です。
使い方の一例をご紹介します。
【例文】
拝啓
処暑の候
〇〇様におかれましては
益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
・
・
暑さの厳しい折柄、くれぐれもご自愛くださいませ。
敬具
まずは「拝啓」などの頭語で始め、「処暑の候」といった季節のあいさつを入れます。
その後「益々ご健勝のことと~」などの安否のあいさつを書き、前文は終わりです。
最後は「敬具」などの結語で締めましょう。
処暑の候の代わりに、「処暑の折」や「処暑のみぎり」などを使ってもいいですよ。
また立秋から処暑の期間(8月7日頃~9月7日頃)は、暦の上では「初秋」にあたります。
実際の季節感とは少しずれてしまいますが「初秋の候」という時候のあいさつも使えるので、覚えておいてくださいね。
処暑の旬の食べ物!サンマやブドウを食べて夏バテ解消

処暑の時期に旬を迎える食べ物には、このようなものがあります。
| フルーツ | 野菜・キノコ | 魚 |
| ブドウ イチジク 梨 スダチ |
茄子 |
サンマ カンパチ イワシ 太刀魚 |
とくに9月頃からスーパーなどに出回り始める「サンマ」は、栄養豊富で夏バテ防止にぴったり。
鉄分、ビタミンA、カルシウム、DHAなど体に嬉しい成分がたくさん入っています。
旬のサンマはとくに脂が乗っておいしいので、ぜひこの時期に味わっておきましょう。
同じく旬のスダチを絞ってかければ、より風味豊かに、サッパリといただけます。
スダチは疲労回復効果のあるクエン酸や、抗酸化作用のあるビタミンCなどが豊富です。
また8月から10月初めにかけて旬を迎える「ブドウ」も、夏バテ解消におすすめです。
ブドウに含まれるブドウ糖や果糖は、疲労回復にもってこい。
ビタミンやミネラルも豊富なので、元気になりたいときに効果的な果物なんです。
処暑に鑑賞できる植物や花は「木槿」「秋の七草」

処暑の時期に楽しめる植物、花はこちら。
- 木槿(むくげ)
- 水引(みずひき)
- 秋の七草
- ホウセンカ
木槿は中国が原産の花で、韓国の国花としても知られています。
ハイビスカスに似た見た目をしており、白・赤・ピンクなどの大きな花が鮮やかです。
水引は、細く真っ直ぐな花穂に、米粒大の小さな小花をつける植物。
紅白の花びらが贈答用の「のし紙」に掛ける水引に似ていることから、この名前がつけられました。
秋の七草は、萩(はぎ)、桔梗(ききょう)、葛(くず)、尾花(おばな)、女郎花(おみなえし)、藤袴(ふじばかま)。
「春の七草」のようにお粥にするわけではなく、観賞用として楽しむ美しい草花です。
尾花とはススキの別名で、この頃になるとススキに花穂(かすい)がつき、黄金色に輝き始めます。
こうした季節の草花が咲き始める様子から、秋の気配を感じることができるでしょう。
処暑の行事「地蔵盆」で子どもたちの健やかな成長を願う
地蔵盆とは、旧暦7月24日に各地で行われてきた地蔵菩薩のお祭りです。
現在は月遅れの8月23日~24日に開催される地域が多いですが、7月24日前後に行われる地域もあります。
地蔵盆の主役は子どもたち。
各町のお地蔵さんを洗い清めて新しい前垂れをかけたり、提灯で飾りつけたりします。
そしてお地蔵さんの前にお菓子やおもちゃなどをお供えし、集まった子どもたちにふるまわれます。
発祥地である京都では、子どもたちがゲームや福引もして楽しむそうですよ。
地域によっては、2~3mもある大きな数珠を子どもたちが囲んでぐるぐる回す「数珠回し」という習慣も。
京都や大阪などの近畿地域や、北陸地方、長野市周辺で盛んに行われていますが、残念ながら東海や関東ではほとんど見られません。
もしお住まいの地域に地蔵盆があるようでしたら、処暑の季節を感じる行事としてぜひ参加してみてはいかがでしょうか。
暑さがおさまる処暑の時期も油断せず元気に乗り切ろう!
今回は、二十四節気のひとつ「処暑」の時期や意味、旬の食べ物や行事などをご紹介しました。
処暑はまだ残暑の厳しい折ですが、残暑見舞いを出すにはギリギリの時期です。
うっかり忘れていたという方は、遅くとも処暑が終わる前には郵送しましょう。
萩や桔梗、ススキといった「秋の七草」を鑑賞できるほか、近畿地方を中心に「地蔵盆」も楽しむことができます。
旬の食べ物はサンマやスダチ、ブドウ、茄子など。
油断すると暑さで体調を崩しやすい季節ですから、栄養豊富な食べ物で夏バテを防止して元気に過ごしてくださいね。