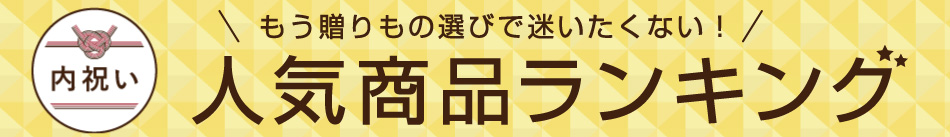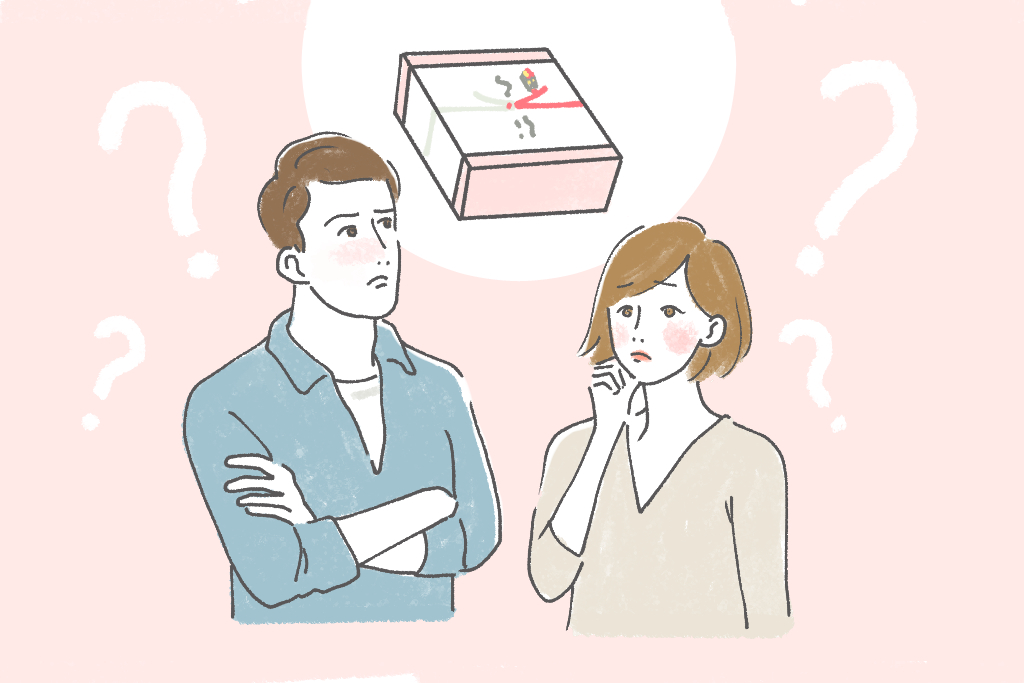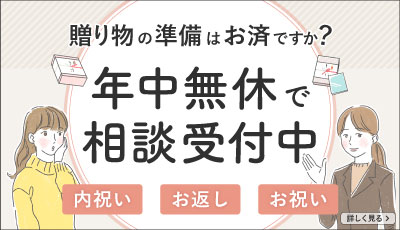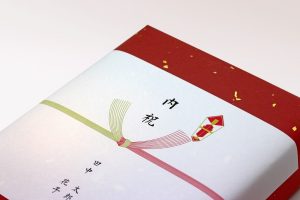結婚祝いのご祝儀やプレゼントをもらったら、もちろんその場でお礼を言いますし、郵送の場合は電話で感謝の気持ちを伝えることがほとんど。
わざわざお礼状を送る必要はないような気がしてしまうかもしれません。
ですが、結婚内祝いを贈る際は、改めてお礼状に感謝の気持ちをしたためるのが好ましいです。
今回はお礼状に使う便箋・封筒の選び方、基本的な書き方や構成などを解説。
フォーマルな縦書きの例文、横書きの堅苦しくない例文もそれぞれご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。
結婚内祝いにはお礼状を添えて!挙式後1ヵ月以内がマナー
結婚祝いへのお礼状は、挙式後または新婚旅行が終わったらなるべく早く出すようにしましょう。
結婚内祝いの品物・お礼状ともに、結婚式から1ヵ月以内、挙式しない場合は結婚祝いをもらってから1ヵ月以内に送るのがマナーです。
お礼状は結婚内祝いの品に同封しても大丈夫。
ただし、結婚祝いをいただいたのが挙式の数ヵ月前だった場合など、お返しを贈るまでに間があいてしまうときはお礼状だけ先に出しておくといいでしょう。
別々で送る場合は、品物より先にお礼状が届くように郵送します。
お祝いに対するお礼を述べ、内祝いの品物は別便で後からお届けすることを伝えてください。
印刷のお礼状にも一言手書きメッセージを添えて
結婚内祝いのお礼状は手書きがベターですが、たくさんの人に贈る場合は時間的に難しいことも多いですよね。
そんなときは基本は印刷にして、余白に手書きで一言メッセージを添えましょう。
直筆でメッセージがあるだけで思いが伝わりますし、ていねいな印象になりますよ。
手渡しの場合はお礼状なしでもOK
結婚内祝いを手渡しする場合は、直接感謝を伝えられるので必ずしもお礼状が必要なわけではありません。
簡単なメッセージカードだけ添えてもいいでしょう。
また、地域によってはお礼状を出さない慣習があることも。
もちろんそのようなケースでもお礼状は不要です。
結婚内祝いに添えるお礼状の便箋・封筒は白無地がベター

結婚内祝いのお礼状は封書(封筒+便箋)が最もフォーマルな形。
上司や目上の方には封書のお礼状を送りましょう。
ポイントは以下のとおりです。
- 白無地(罫線のみ)の便箋を使う
- 封筒は白無地の二重封筒
- フォーマルにするなら縦書きの便箋
- 筆ペンや万年筆・インク型のペンで書く
厚手の上質な便箋を使うとフォーマル感が出ます。
柄入りを使いたい場合は、ウエディング用や、季節感のあるシンプルな柄であれば構いません。
便箋はシンプルなタイプなら横書きでも大丈夫ですが、目上の方には縦書きのほうがフォーマル感が出るのでおすすめ。
封筒は白無地の二重封筒が最も格式高いです。
お礼状は宛先も含めて黒か青の万年筆またはインク型のペン、筆ペンで書くとていねい。
目上の方など改まった相手には、なるべくボールペンではなく万年筆などを使いましょう。
一筆箋やはがき、メッセージカードは親しい友人や同僚など、近しい関係の方に使うといいですよ。
結婚内祝いのお礼状の書き方!基本を押さえておこう
マナーに厳しい目上の方に送るときなど、なるべくしきたりに則りたい場合は以下のポイントを押さえておきましょう。
- 手書き(縦書き)の封書にする
- 2枚以上の便箋を入れる
- 行の頭をそろえる(段落の始めに文頭を下げない)
- 句読点を打たない
- 忌み言葉・重ね言葉を使わない
フォーマルなお礼状にしたいときは、縦書きの便箋を使って手書きにします。
1枚目の便箋に内容がおさまる場合は、白紙の便箋を入れて2枚にしましょう。
行頭や句読点についてはあくまで慣例なので、マストではありませんがマナーに厳しい方に送る際は押さえておくといいですよ。
結婚内祝いのお礼状の基本的な構成
お礼状の基本的な流れは、以下のとおりです。
- 頭語・時候のあいさつ
- お祝いへのお礼や品物の感想
- 結婚内祝いを送った(または後日送る)ことの報告
- 新生活の様子や近況報告
- 今後のお付き合いや支援のお願い
- 結びのあいさつ・結語
目上の方などに改まった形でお礼状を出すときは、頭語(「拝啓」など)、季節を表す時候のあいさつや安否を尋ねるあいさつから成る「前文」から書き始めます。
その後、お礼の言葉や内祝いについて、近況報告などの「主文」を記しましょう。
最後に、手紙文を締めくくる結びのあいさつと、結語(「敬具」など)から成る「末文」を書いて終了です。
上司や目上の方に!フォーマルな結婚内祝いお礼状の例文
ここからは、縦書きのフォーマルなお礼状の例文をご紹介します。
少し堅苦しく感じるかもしれませんが、上司などの目上の方や、礼儀に厳しい方にはこのような慣例に則ったお礼状にするといいでしょう。
【例文】
拝啓
山々の緑も色濃くなりましたが お健やかにお過ごしのことと存じます
この度は私どもの結婚に際し暖かいお心遣いを賜り 本当にありがとうございました
頂戴したお祝いでティーセットを購入いたしました
毎朝二人でおいしい紅茶を楽しませていただき 新生活により潤いが増しております
内祝いのしるしに心ばかりの品を別便にてお贈りしましたのでお納めください
至らない二人ではございますが 力を合わせて温かい家庭をつくっていく所存です
今後とも温かくご指導くださいますようお願い申し上げます
季節の変わり目ですので お風邪など召されぬようどうぞご自愛くださいませ
敬具
親しい友人や親戚には横書きでもOK!堅苦しくないお礼状の例文

ここまではフォーマルなお礼状の書き方をご紹介してきましたが、気心の知れた親戚や親しい友人などには横書きの堅苦しくない文体でも構いません。
友人や同僚であれば、頭語や時候のあいさつなども省いてしまって大丈夫です。
例文をご紹介しますね。
【例文:親戚へのお礼状】
拝啓
暑さの厳しい日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
この度は私達の結婚祝いに素敵な品をいただき、ありがとうございました。
便利で使いやすく、私も〇〇さんもとても気に入っています。
感謝の気持ちを込めて、ささやかながら内祝の品をお贈りします。
いただいたお鍋でおいしい料理を作りますから、ぜひ新居にも遊びにいらしてください。
未熟な二人ですがこれからも夫婦共々よろしくお願いいたします。
敬具
【例文:友人へのお礼状】
結婚のお祝い本当にありがとう!
さっそく新生活に必要な物をそろえるために役立たせてもらってるよ。
ささやかだけど、内祝いの品を贈ります。
近くまで来たときはぜひ気軽に新居へ遊びに来てね。
これからもよろしく!
結婚内祝いのお礼状を写真入りカードにするのもアリ

結婚内祝いのお礼状として、新郎新婦の写真入りメッセージカードを使う方法もあります。
株式会社ウエディングパークが100人を対象に行った調査によると、内祝いに写真入りのメッセージカードを使った人は約22%。
写真を入れなかった人が約78%と、通常のメッセージカードを選んだケースが3倍以上多いという結果でした。
写真入りにした人、しなかった人、それぞれの理由は以下のとおりです。
<写真入りにした理由>
- 結婚式場で用意されたものをそのまま使ったから
- 相手から写真を送ってほしいと言われていたため
- 挙式していないため夫と面識がない人も多く、結婚のあいさつも兼ねていたので
- 結婚式に出席していない人にドレス姿を披露したかった
挙式していない場合もウエディングフォトの写真を使えば、新郎新婦のどちらかと面識のない人にお披露目することができて便利。
また、結婚式に出席していない人にドレス姿を見てもらえる点もいいですね。
<写真を入れなかった理由>
- 写真入りのカードは処分しづらく、扱いに困ってしまうだろうから
- 写真は年賀状で送ればいいと思ったので
- そのようなサービスがあることを知らなかった
主な理由は、あげた相手が扱いに困ってしまうかもしれない、捨てられたら悲しいから、というものでした。
確かに贈る相手のことを考えると、写真なしにしたほうが無難な場合もありそうですね。
また「近いうちに年賀状で写真を送る予定があるため必要ない」と判断した人も多いです。
年賀状を写真入りにするならメッセージカードは写真なし。
挙式していない場合や、結婚式に出席していない人には写真入りにする、というようにケースによって最適な方法を選ぶといいでしょう。
結婚内祝いにはお礼状を添えて感謝の気持ちを伝えよう
結婚内祝いを配送するときは、お礼状を同封するか別便で先に郵送して、改めてお祝いをいただいた方々に感謝の気持ちを伝えましょう。
目上の方には白無地の便箋を使うのがベターですが、手渡しの場合や親しい友人などには簡単なメッセージカードでも構いません。
内容は、頭語・結語を使い、お礼の気持ちや結婚内祝いを贈ること、近況などを手書きで記すのがフォーマルです。
気心の知れた友人や親戚などであれば、横書きの堅苦しくない文章でも大丈夫。
挙式しない場合などは、写真入りカードにしてドレス姿をお披露目してもいいですね。
結婚内祝いにはマナーを押さえたお礼状を添えて、今後もよいお付き合いができるようにしましょう。
親戚に送る結婚内祝いに必要なメッセージやプレゼントなど相場や仕様を一挙紹介
親戚の結婚内祝いに最適なプレゼントやメッセージ、注文方法や渡し方まで詳しく… 記事を読む
職場に送る結婚内祝いに人気な、おしゃれでおいしいお菓子ギフト
職場に送る結婚内祝いの品は、結婚の記念に送ってもらったお祝い品に対してお礼を… 記事を読む

[六本木アマンド]六本木ハイカラナッツ
ナッツを手軽に味わえるスクエア状の焼き菓子。粒が残る程度に細かく砕いたことで、口の中でナッツとフレーバーが程よく香るサクッと軽い食感に仕上がりました。